2025年10月11日 11:00
もっと見る 
感謝感激です!!❤ありがとうございます
2025年11月28日 08:12 いいね0件 返信0件
Very をやっていますが、いくつか質問があります!
・音価通りに弾いて(2分音符などを短くせず、きちんと長く弾いて)
・音価通りに弾いて(2分音符などを短くせず、きちんと長く弾いて)
2025年11月22日 20:51 いいね0件 返信0件
奏先生、音大て入学にあたって身元保証人を取られますか??自分は家族から1人、親族から1人=オジを取られましたね。問題なく卒業して良かったですね😅首都圏の私大です
2025年10月25日 16:19 いいね0件 返信0件
鉛筆の芯ほどの太さのシャーペン使ってます。もちろん2Bです。アリだと思います!
2025年10月21日 23:00 いいね0件 返信0件
全部守れていた。よかった。
2025年10月21日 16:27 いいね0件 返信0件
アルコはボーイングの記号も書くとよいですね?
グシュターベにはマーカーで塗っておくと、追うのが楽です。プロは練習回数少ないんで不要でしょうけど。
うちの先生は教えてくれるんだけど、みんなのレベルが低すぎてそのありがたみが理解できてないんですよね。勿体ない。
グシュターベにはマーカーで塗っておくと、追うのが楽です。プロは練習回数少ないんで不要でしょうけど。
うちの先生は教えてくれるんだけど、みんなのレベルが低すぎてそのありがたみが理解できてないんですよね。勿体ない。
2025年10月21日 03:05 いいね0件 返信1件
ボーイングの記号!ありof ありです!
2025年10月21日 20:12 いいね0件
すみません、半音の指くっつけるマークは、書いてもセーフでしょうか?😅
2025年10月20日 11:19 いいね0件 返信1件
私も半音階に見せて途中ここだけ全音、みたいな時、反応できないので、全音マーク書いたりしちゃいます😅
スタンドパートナーにはゴメンね、読みづらい?許して〜と逃げを打ってる😂
スタンドパートナーにはゴメンね、読みづらい?許して〜と逃げを打ってる😂
2025年11月8日 21:52 いいね0件
市民合唱団で歌ってます。とても参考になりました。ありがとうございます。
2025年10月19日 02:18 いいね0件 返信0件
すてきな動画ありがとうございます。とても助かります。
質問です。5線の下に書くのか上に書くのかは決まっていますか??💦
例えば速度は上、強弱は下など!
質問です。5線の下に書くのか上に書くのかは決まっていますか??💦
例えば速度は上、強弱は下など!
2025年10月16日 15:44 いいね0件 返信0件
この方は歌手の方ですか?
2025年10月16日 04:34 いいね0件 返信0件
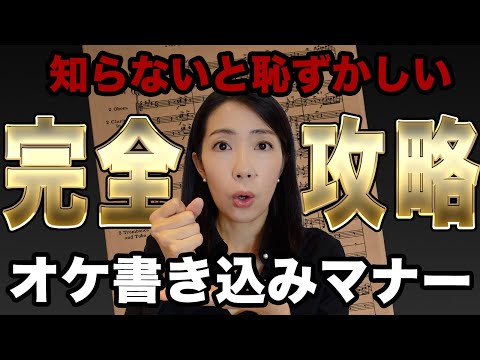


※2025年10月19日(日)、海外情報を補足しました※
高評価&チャンネル登録が次の動画づくりの励みになります!🙏
⏱目次⏱
0:00 オープニング 〜 本動画の視聴メリット
4:38 ダメな書き込みの例
5:05 楽譜書き込みの大原則
6:02 書き込みの「前準備」
7:55 ①動作指示系
8:04 👓:指揮者を見る
8:24 V.S.:譜面をめくる
8:56 小節休み
10:29 ミュート着脱記号
11:07 ②テンポ・拍数系
11:26 →、←、〰:早く、遅く
11:58 in2 in3 in4 etc
12:28 ③強弱系
12:42 「だんだん小さく」「もっと大きく、小さく」
13:04 強弱の「突然〇〇!」
13:21 次の段で突然強弱が変わるとき
13:33 ④奏法指示
13:44 コンマ:余韻を残しつつ音を分離、斜線:音楽を分断
14:27 N.V.または non vib:ビブラートをかけないで ⇔ con vib.ビブラートをかけて
14:51 △:Pizzicato ◯: arco
15:31 ON:弓をつけてひく、OFF:弓をとばす、半トバシ
15:46 弓先、弓元、sul tasto:指板寄りで、sul pont.:駒寄りで
15:57 弓順は真上に書く!
16:22 その他
16:37 まめ譜・カンペ:長い休符あけの入りのため、または主旋律を尊重する役割
17:24 音色指示( dolce:やわらかく、espress.:うたって、その他表現)
17:52 やってはいけない①
19:46 やってはいけない②
21:25 改善ビフォーアフター
▼本日の要約(超圧縮)
✨伝わる書き込みができる=頭の中が整理されていて上達する✨
この動画では、オーケストラの楽譜書き込みをするときに気をつけるべきポイントを大解説!
オケには入っていないけど、個人レッスン受けてるよ!という人にも役に立ちます。
-------
▼海外プロ奏者からの補足
私がいつも大変お世話になっているお二人のプロ奏者から、
今回の動画への補足をいただきました!!感動、感激、ありがたすぎます⋯!✨
🇩🇪👨⚕ドイツでのキャリアをお持ちの大御所プロ(お名前は伏せます)
ドイツなどヨーロッパでは以下の区別が明確に意識されています。
・テンポ関係の指示(rit., accel., tempo I など) → 五線の上に書く
・表情・ニュアンス関係の指示(espressivo, dolce, cantabile など) → 五線の下に書く
「下に波線を書くと、テンポというよりは、「しっかり」とか「esp.」とかみたいな感じの指示になります。
なので、文字で書き込む時も、五線の上下に書き分けるとベターなのかも」
🇫🇷👨⚕小島燎さん(フランス国立オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ管弦楽団コンサートマスター )
〜フランスのオケ現場の筆記事情と文化の違い豆知識〜
■ 鉛筆文化の違い(これはフランス全体に共通する傾向かも)
・フランスでは濃い鉛筆を使う人が非常に少ない。
・スーパーなどで手に入る文房具の品質が日本より低い。
・日本製の濃い鉛筆を使うと「濃すぎて消えない!」と言われるほど
■ 修正テープ・ボールペン文化
・小島さんのオケでは修正テープやボールペン使用があるが、は所属オケ(室内オケ)特有の事情かも
・指揮者・コンマスが変わるたびにボウイングやフィンガリングが頻繁に変更。
・スキャンPDFや独自版を使うことも多く、常に書き換え・修正が発生する。
→そのため、修正テープやボールペンが実務的に必要になる。
■ 書き込みの特徴(演奏面)
・小島さんのオケでは純正律で音程を取るため、矢印記号(高め/低め)を多用。
・フレーズ方向を示す曲線矢印なども頻出。
・「この音にアクセント禁止」などのアクセント消しマークもよく書く。
・ベテラン奏者(例:勤続40年のチェロ首席)は全音に指遣い記入。
→小島さんのオケならではの、個別の書き込み文化。
■ 楽譜・ライブラリアン事情
・小島さんのオケでは、常勤ライブラリアンが最近まで不在。
・楽譜整理や譜めくりなどを各プルトで自己解決。
・紙の製本テープがなく、セロテープでベタ貼りが一般的。
■ フランス全体の現場感
・一方で、フランス国立管・オペラ座など伝統系オケは独自文化を保っている印象。
・現場によってかなり差がある。
・他アンサンブルでは、筆記具を持ってこない奏者も多く、効率が悪いという現実も。
--------
高評価・チャンネル登録、そしてX・インスタ・ブログ・サブチャンネルのフォローもお願いします🙏
お調べいただいたり、お仲間に声をかけたりと本当に大変だったかと思いますが、心から感謝です!仲間にも共有させていただきます。
自分がNGの書き込みをしまくっていたことに気づきました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
ところで「イイネ」も初めて押しましたが、音符になるんですね。
とても可愛くて気に入りました。
いつも楽しく観させていただいています。ちょっと付け加えたいことがあります。
左向き矢印『←』と波線の違いは、そのテンポのテンションの違いです。 同じゆっくりになるのでも、左向き矢印は段々ブレーキがかかる=テンションが強まる感じで、逆に波線は段々とテンションが緩む感じです。
アメリカオケでは弓先がTip、元弓がFr.。
イタリアオケでは弓先がpunta、元弓がTallone、上半弓はM.S. (Metà Superiore の略)、下半弓はM.I. (Metà Inferiore の略)、中弓はMetà。
あと、どの国でも基本的に元々プリントされている記号を丸や三角で囲むのは、タブーです。
三角を使うのは、指揮者の振り方のみ。例えると、8分の5拍子(5/8)があって2+3で振る時は、五線譜の上に 『 / △ 』と書きます。7/8で2+2+3で振るのなら『 / / △ 』みたいな感じです。
他のパートを聴きながらそれに寄り添ったり合わせて弾く場合は 『ファゴットを聴く』なんて書かず『Fg.』とだけ書きます。
指揮者がココから急にテンポを速くする場合は五線の上に 『 + mosso』 と書きます。
ご参考までに!
プロの方は譜面は楽団所有ですし、弦楽器は2人で一つの楽譜を見るので特に気を遣いますよね。
アマチュアは殆どが本番譜が練習譜を兼ねます。そして管楽器は頁数もバイオリンより遥かに少ないので、楽団所有の原譜をコピーしてして自分用の楽譜を作ります。しかも管楽器はお一人様用なので楽です。
仰有る通り、書込みを「読解」するでは間に合わない。同じ様な記号を使って居ることも沢山有りました(笑)
管楽器で困るのがブレス。この先、ずーっとブレスするところがない、なんて箇所は大きくVを書いちゃいます 。生命の危機となるので(笑)
後、曲の冒頭等で、ゆったり響かせたい時には「息を吸え」なんて書きます⇒5文字以内なのでセーフでした(笑)
今まではいきなり強弱が変わる場所には"sub."と大書してました。
矢印と波線は中・高生の吹奏楽部時代から使っていて、周りの仲間の書き込みよりかなりシンプルに見やすくするよう意識してました。
楽団員の苦労や工夫がとても面白く見ることができました。